裁判官の「心証」形成について(第4回)
1 裁判所は、誰を尋問するかについてどのように考えるのか
前々回説明しましたように、訴訟の終盤とは、尋問をするのかしないのか、するとして誰をするのか、というのが問題となる時期です。これまで、説明したところによれば、尋問の実施の有無及び誰を尋問するのかを決めるまでの間には、裁判所は、争点は何かということを把握した上で、時には、積極的に当事者に質問をするなどして、それについての証拠には何があるのか、あるいは、争点に関する当事者の言い分は何か、ということは既に確認されていることになります。逆に、何故このようなことを確認した後に尋問を実施について判断をするかというと、争点整理というものが、そもそも尋問で事実を認定しようとする争点を絞り込んでいくという側面を有しているからです。
尋問で事実を認定する、というのはやや分かりにくい表現かとも思いますので敷衍して説明します。
例えば、ある日の東証平均株価の終値がいくらだったのか、ということが争いになっていた場合、それが実際にいくらだったのか、ということについては、客観的な証拠がいくらでもあるわけですので、このようなことについて、尋問をするのは時間の無駄といえるでしょう。あるいは、一般的な銀行の融資において、銀行が融資したといっているのに、契約書や申込書などの書類がないといったら、銀行員がいくら金を貸したと証言しても、ほとんどの場合、融資がされたと認められることはないでしょうから、尋問をする必要性は低いように思われます。逆に、貸した金を返してほしいという訴訟において、被告は、お金は受け取ったが、もらった(贈与された)ものだ、といって争っているとすれば、お金が原告から被告に渡った(交付された)ことは当事者間に争いがないと思われますが、このような場合、尋問をするまでもなくお金が交付されたという事実はあると判断できると思われます。
そのほか、お金を貸したかどうかが争いになっている訴訟で、お金を借りたとされている人のある日の朝食が何だったのか、ということについては、通常は、尋問をして事実が分かったとしても、お金を貸したかどうかの認定に役に立たないですから、ある日の朝食が何であったかについて尋問をするとは考えにくいです。
上記の例はいずれもかなり極端で分かりやすいたとえですが、要するに争点を絞り込むというのは、①尋問をするまでもなく、ある事実があったかどうかを判断できるものや、②そもそも事実を認定をしても意味がないものを尋問の対象から除く作業をいいます。
言い換えると、尋問は、認定することに意味がある争点について、認定するために尋問を経た方が良いと考えられる争点についてされるものであるといえます。また、誰を尋問するかについては、それに関係している者をするということになるのであって、それ以外の場合については尋問をしても仕方がないのでやらない、というのが理念的な模範解答ということになります。
2 尋問の実際
原則的には上記のようにようにいえるとしても、実際上は、もう少し様々な事情が考慮されているように思われます。
何故、理念どおりにされないのかというと、それは、一つには、認定する意味があるかどうか、というのは上記の例ほど簡単に割り切れるものでもないからです。例えば、お金を貸したかどうかが争いになっている事件について、上記の例にあるような、ある日の朝食がなんであったかは明白に関係ないでしょうが、金を貸したとされている人が、太っ腹な性格だったとか、金を借りた側がある時期羽振りが良くなったといった事実は、(私の感覚では)ダイレクトに関係はしていないものの、全く関係がないか、と言うのもためらわれます。
また、裁判官は、当事者がある事実を立証するための尋問申請を却下した上で、証拠がないから認めないという判断をするのは、裁判所の公平らしさを疑わせることにならないか、ということも懸念しがちであるように思います(もちろん、不利益な判断をするから、どのような尋問申請でも認めるというわけではありませんので、あくまで傾向の話ですが、裁判所は尋問の申請段階では「負かす方にやさしい」傾向があるとは言えるように思います。)。そして、一方からの尋問申請を採用して、もう一方の当事者からの尋問申請を却下するのもやはり不公平に見えることを嫌って、結局双方の尋問を採用するということも多くあるように思います。
要するに、ある程度客観的な証拠だけで事実認定ができる場合を除くと、多くの事案では双方当事者、あるいは関係者を尋問することが多いというのが私の印象です。
3 裁判所は尋問をどれほど重視しているのか
ところで、裁判の結果は、尋問前には決まっている(尋問をしても結論は変わらない)、などと言われることがあります。もちろん、正面切ってそのように問われると、ケースバイケースです、としか言えないですし、性質上、統計的なデータを示せるわけではありませんが、確かに、尋問をしても心証はあまり動かない、という場合は多いように思います。それは、上記の説明を敷衍してみればある程度は理由が分かるのではないかと思います。
すなわち、そもそも尋問をするのは、「客観的な書証で認定できたり、当事者間に争いのない事実」ではない事実を認定するためです。そしてそこに争いがあるからこそ尋問をするわけですから、多くの場合、双方の言い分は食い違う訳ですが、そうすると、よほど、片方の言い分が不合理であったり、嘘をついているということが客観的に認められる、というような場合でなければ、結局、尋問を経ても、双方の言い分が食い違うという以上のことは分からないことも多いのです。
そして、裁判においては、立証責任という概念があります。これは、ある物事の存否が分からない場合には、それを要件とする自己に有利な法律効果が認められないという不利益をいいます。定義だけ聞いてもよく分からないと思いますが、たとえば、お金を貸したから返してほしい、という事件においては、貸したという側は、(他にも要件はありますが)そもそもお金を渡したということについて立証責任を負っていますので、お金を渡した(=ある物事の存否)かどうかが分からない場合、お金を返してもらうという「自己に有利な法律効果」が発生しない、ということになるのです。
これを組み合わせて考えますと、結局、お金が渡されたかどうかが「客観的な証拠で認定でき」ないで尋問になり、双方の言い分が平行線になった場合、お金が渡ったかどうかは不明、すなわち、お金を返してもらうという原告に有利な法律効果は発生しない、ということになりがちです。
要するに、尋問前に結論が決まっているといわれるのは、①証拠からは存否がはっきりしない事実について、尋問をしても双方の言い分は平行線のままであり、事実の存否ははっきりせず、②その事実の存否がはっきりしない場合、立証責任を負っている側が不利益な判断を受ける、という筋道をたどり、③結果としては、尋問をしなくても結論は変わらない、という事案が、それなりに、あるいは非常に多いという経験則に基づくものということができます。
物事の性質上、上記経験則がどの程度確かなのか、というのは、実証的に明らかにするのは難しいので、どこまでいっても印象論的な話になるということを前提にお聞きいただきたいですが、やはり多くの書籍等でいわれているとおり(ニュアンス等には相違があるとは思われるものの)、やはり上記経験則は良くも悪くも相当程度正鵠を射ているように思います。この点は、ある種のドラマや、裁判を題材にしたゲームとは違うように思われます。
しかし、すべての事件で尋問は無意味かというとそうとはいえないというのが私の印象です。これまで裁判の進行について説明をしてきましたが、常にあらゆる手続が理想的に行われるわけではありませんので、尋問を実施した結果、裁判官の事案の見立てが変化した、ということは必然的に生じ得ますし、私自身の裁判官としての経験に照らしても、そうしたことはそれなりの頻度で生じているという印象があります。この点、結論が180度変わるということはさすがに少ないとは思いますが、それでも、尋問によって、一部の事実関係についての印象が変わることが全体に影響することはないではないと思いますし、例えば、慰謝料の金額などのように、客観的な計算方法がないものなどは、尋問によって結論が変わる頻度はそれよりも高いのではないでしょうか。
4 尋問後の流れ
いずれにしましても、 尋問後にはしばしば、裁判所から和解勧試がされます。その結果、相応の事案では和解に至ることもありますし、そうでない場合には、(総括的な主張の機会がある場合もありますが、)数か月以内に判決が下されるというのが尋問後の一般的な流れとなります。
5 当事者として尋問についてどのように対応すべきか
以上を踏まえて当事者として尋問についてどのように臨むべきか、ということについて考えると、上記のように絶対的ではないとはいえ、やはり客観的な書証等が大事であることを否定できない以上、やはり、書証を立証の柱と考えるのが良いということになりますし、書証によってはその存否が明確にならない事実については、水掛け論に終わる可能性を常に念頭に置いておくべきといえようかと思います。この点、訴訟は客観的な事実を探求することを目的とする一面はあるとは思いますが、所詮は神ならざる人間の行いであって、真実が明らかにならないことはいくらでもある、ということは覚悟しておかなければならないように思います。
なお、訴訟の各段階における裁判官の心証形成というテーマから外れますが、上記のようなことがあるからこそ、弁護士は、訴訟になる前の段階から、訴訟において、どのような立証手段があるのか、特に客観的な証拠はあるのか、ということをシビアに検討しますし、紛争になる前の段階から関与している場合(例えば、会社の顧問などをしている場合)、トラブルになった場合に備えて、このような証拠を残しておくべきである、といったことをアドバイスもするのです。
話を元に戻しますと、上記のように印象が変わることによる不利益を避けるためには、それ以前の主張整理段階から、主張のあり方については考えておく必要があると思います。すなわち、裁判官の印象をよくしようと思うあまりにそれ以前の主張や立証において、実態をゆがめて、きれいに言いつくろいすぎてしまうことは、その場の短期的な印象をよくしたとしても、尋問段階でそれが破綻すると、かえって利益を損なう可能性を高めることにもなりかねません。もちろん、訴訟ですので、何も自身に不利なことを何でもかんでも認めて言い訳をするな、と言っているわけではありませんが、尋問以前の段階から、事案に関与していない第三者(裁判官)に実態を歪めて伝えるような主張になっていないか、ということも考慮することが必要でしょう。
また、尋問申請段階においては、色々なことを言いたい、説明したいという思いから、多くの人の尋問申請をしたり、長時間の尋問を申請する方もいますが、裁判所はできるだけ争点にフォーカスして行いたいという姿勢ですので、それがすべて認められないことも念頭に置かざるを得ないと思います。もちろん必要があればそれを裁判所に丁寧に説明し理解を求める努力をすべきではありますが、現実問題としてそれが認められないというのであれば、認められた範囲内の尋問の中でできるだけ効果的な尋問を行うよう努めるほかありません(なお、どのような尋問が効果的であるかについては、別の機会に説明したいと思います。)。
次に、尋問後にされる場合が多い和解勧試についてですが、上述したように、尋問は、訴訟の終盤であるということからしますと、この段階における和解勧試は、裁判官は、基本的には判決の結論を見据えて行います。端的にいえば、判決になった場合に、負ける可能性が高いと裁判官がいうのであれば、判決になれば敗訴を覚悟する必要があります。もちろん、判決については不服があれば上訴できるわけですから裁判所の心証開示が絶対的な結論というわけではありませんが、統計的に見て上訴で結論が変わる可能性は高くはないことからしても、裁判所からの和解勧試にどのように対応するかについては、判決になった場合のリスクやコストをきちんと考慮して検討する必要があります。
6 最後に
4度にわたって、民事裁判の1新段階における裁判所の心証形成のあり方について説明してきました。上記を踏まえ、現在私は弁護士ですので、弁護士の立場から申しますと、裁判で有利な心証を得るためのアクロバティックな手段というものがあるわけではないと思う一方、最終的に効果的な主張立証を行うためには、訴訟全体の流れを見据え、事案を当事者として体験していない裁判官に対してどのように説明すべきか、という観点を踏まえる必要があることがお分かりいただけたのではないでしょうか。ただし、私自身、裁判官として、あるいは弁護士として、様々な事案を経験する中で、建前ではなく一つとして同じ事件はない、ということを痛感しておりまして、実際には、訴訟の進行についても多くのバリエーションがあると思っております。上記の説明も、裁判官の経歴を持つ弁護士として、経験に基づき説明させていただいてはおりますが、性質上、例外もある一般論であることにはご注意いただき、具体的な事案についてのより個別的なアドバイスが必要な場合は、弊所にご相談いただくことをご検討ください。
余談となりますが、弊所のウェブサイトに検索でたどり着かれる方の検索ワードを調べてみますと、「裁判官の心証」というものが多くあります。裁判手続きというのは、非常にテクニカルな部分もありますし、これまでも触れてきたように裁判官はポーカーフェイスで何を考えているか分からない方も多く、不安に思っておられる方も多いのでしょう。私のご説明がそうした方々のお役に立てれば幸いです。
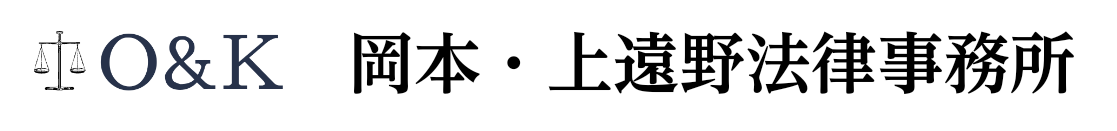


先生、裁判官の心証について話しをして頂いて大変勉強になりました。
私は、現在原告で、民事控訴審(労災不支給取り消し)で審理中です。内容は長文なるので省きますが、異例ですが8回の口頭弁論、証人尋問、当事者尋問を行い来週、最終準備書面を出して結審します。行政訴訟は和解が無いと聞きますが、裁判官の心証も無いのでしょうか、私の案件も裁判官からの心証があれば聞きたく思いました。
大変申し訳ありませんが、コメント欄では個別の事案についての言及は致しておりません。恐縮ですが諸事情をご賢察いただけますと幸いです。
証人申請について、教えていただきたいです。第1審(地裁)で、損害賠償と名誉毀損の回復措置について本人訴訟で争っています。重要な書証はすべて被告側が所持していますが、被告はそれを出してきません。争点にかかわりのある判決に影響を及ぼすと思われる書証の文書提出命令申立てをしましたがすべて却下されました。求釈明も、被告は「釈明はしない」といい、裁判官からは「釈明は求めない」と宣告されました。後、残るは被告側の人を証人申請して、「嘘のない」証言を引き出すしかありません。申請する証人の承諾を得られていない場合でも、証人申請することは可能でしょうか?上記の状況で、認められる可能性はどうでしょうか?よろしくお願いいたします。
MN様
大変恐縮ですが、個別の事案についてのコメントは致しかねます。必要であれば、私ないし他の弁護士に法律相談されることをご検討ください。