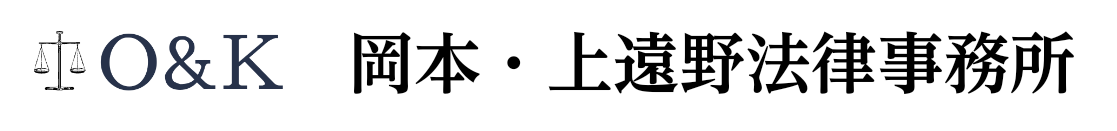記憶と真実の間
記憶はあいまいなのですが、たしか、学生の頃に、新聞だったか書籍だったかで読んだエッセイで以下のようなものがありました。
すなわち、筆者は、学生時代に、友人と悪さをしたか何かで、教師に自分だけ殴られたそうなのです。この点、筆者は、自分だけが殴られたのは、(友人が、筆者に責任をかぶせるような発言をしたというような)その友人に原因があると記憶しているとのことでした。ところが、時は流れ、その友人と話したときに、その友人は、筆者に対し、筆者だけが殴られたのは、たまたま列の一番端にいたからで、運が悪かったのだ、というようなことを言われたというのだけれど、筆者には、その友人が嘘をついているようには感じられなかったというのです。このような出来事を踏まえ、筆者は、人の記憶は不確かだし、自分の都合の良いように変容させるものだ、というような結論を導いていたように思います。概要このようなエッセイを読み、学生時代の私は、なるほど、 筆者の友人が罪悪感などが原因で、記憶を無意識的に変容させるというのはありそうなことであり、人間というものは面白いものだ、と思ったように記憶しています。
その後、法律を勉強するようになり、供述証拠は、その性質上、知覚、記憶、叙述の過程に誤りが発生しうる(からこそ、反対尋問によるチェックが必要)などと言われるということを学んだときにも、上記のエッセイを思い出しました。あるいは、その後、裁判官となり、他者の供述について、それが信用できるとかできない、といったことを判断しなければならない立場になったときに、多くの証人や当事者が相矛盾する供述をしており、どれも一応証拠関係に照らして不合理ではないように見える上、各人に嘘をついている自覚はない(ように見える)こともしばしばあって頭を悩ませるようになると、ますます、「記憶は変容する」という信念は強化されることとなりました。
実際問題、ウィトゲンシュタインとポパーの論争についての有名なエピソードを挙げるまでもなく、注意深いから、知性が高いから、中立的な立場だから、嘘はつくまいとする誠実な人柄であるから、記憶が変容しない、とはいえないのであって、「記憶は変容する」というのは、人の本質的な問題であるような気がするというのが、経験を通じた私のかなり強固な実感なのです(哲学者であれば、問題の所在につき、もっと別のとらえ方をするのかもしれませんが、浅学の身故、深入りできません。)。
というのが、前振りなのですが、実は、冒頭のエッセイを読んだときに、上記とは別の一つの疑問を感じたように記憶しています。
すなわち、筆者自身が、集団でいたずらか何かをした際に、自分だけが教師に殴られたという理不尽さを恨みに思うがあまり、友人に責任転嫁された、という風に記憶を変容させたということだって、ありそうな話なのではないか、と思ったのです。そして、そうだとすれば、そのエッセイの作者は、自分については、記憶を無意識に変容させる可能性を考慮していない点で、やや見方が浅はかなのではないか、というような(小生意気な)疑問を感じたのです。そしてそうであるからこそ、このエッセイが印象に残り、今でもしつこく記憶しているような気がするのです。
他方で、冒頭で申し上げたとおり、実は私は、上記のエッセイにつきその筆者も覚えていなければ、具体的な筋立てもあいまいにしか記憶していません。例えば、殴られる原因となった「悪さ」というのも、割とシビアないたずらであったからこそ、教師にぶん殴られたのだし、友人の自己保身に憤ったという話だったような気もする一方、逆に、他愛のないいいたずらであるにもかかわらず、教師に過剰な暴力を振るわれたがゆえに、強く印象に残っているというような話であったようにも思われるのです。また、作者だけが殴られた理由についての筆者とその友人の認識についての記載も、完全に上記のとおりであったかについてもまったく自信がもてません。
そして、このように記憶があいまいなのであるなら、作者が浅はかだと思った、という私の記憶についても、果たして本当なのだろうか、ひょっとしたら、エッセイにおいても作者は自分の記憶違いにも言及していたのに、あたかも私がそれを自分の手柄だというために、そこを都合よく忘れてしまったのではないか、あるいは、エッセイはもともと別の観点に着目した話であったのに、私のキャリアを通じて得られた「記憶は変容する」というテーゼをうまく説明するためのいわば都合のよい「エピソード」として、エッセイの筋立てを自分の都合のよいように歪めて記憶しているのではないか、という疑念もまた払しょくできないのです。
はたまた、このように二段構えで書いていること自体、自分だけは、無意識的な記憶の変容という問題に誠実に、少なくとも中立的に向かい合っている、という風に言いたいがために、エッセイの内容について中途半端に忘れてしまったような気さえします。
などといっていると、どうにもこうにも頭がくらくらしてきます。そんなわけで、もしも冒頭のエッセイについてご存じの方がいれば、教えてくださると幸甚です。
なお、法律事務所のウェブサイトに記載されたブログですので、最後に無理やりに法律の話に引き付けるとすると、当事者が、いかに記憶どおりのことしかいっていない、といっても、時として、裁判官が裏付けのない供述証拠に極めて冷淡であるのは、多くの裁判官が、表現はともかくとして、「記憶は変容する」(から信用できない)と経験的に強く認識していることにもその理由の一端があるような気がします。そして、そうであるからこそ、弁護士としては、相談者に対し、証拠はあるのか、ということをきわめてしつこく確認したり、証拠がないのであれば、(真実はともあれ、)裁判に持ち込むのはやめた方がよい、などとアドバイスせざるを得ないときもあることをご理解いただければと思います。