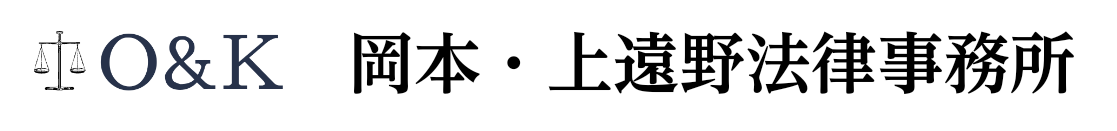法律家と自己紹介
裁判官は転勤がつきものですので、転勤をするたびに自己紹介をします。そこで、よく使われる要素としては、これまでの経歴、配属部、抱負のほか、その地域についての感想などがあります。
例えば、私が、那覇地裁石垣支部に転勤したときなどは、「58期の岡本陽平と申します。初任は東京で民事事件を担当し、その間、留学でアメリカに行きました。帰国後は最高裁の秘書課での勤務を経て、法整備支援でカンボジアに赴任し、再度の帰国後は、松山地裁で民事事件を担当しました。民事以外の経験は少ないのですが、石垣支部では刑事、少年、家事もやることとなる上、支部長としての業務もあって少し不安もありますが、一所懸命頑張ります。なお、沖縄に来るのは初めてで地縁血縁もないのですが、せっかくの機会ですので、ダイビングと三線を体験したいです。よろしくお願いします。」などといった具合の挨拶をしたのではないかと思います。
裁判官の世界は割と狭いので、経歴が明らかになると、どこかで勤務地がかぶっていたり、共通の知人が見つかったりするので、話を弾ませるにはよい材料だったりするのだと思います。
自己紹介はときにすごく短くまとめなければならない時もあり、その場合、要素を削ぎ落としていくのですが、多分、最後まで残るのが「修習期」です。すなわち、一番シンプルな自己紹介は、「58期の岡本です。」になります。
修習というのは、司法試験合格後、原則として受けることになっている司法修習のことで、昭和22年に修習所に入所した方が1期生となり、それ以来続いている数字となります。すなわち、修習期とは、自分がいつ司法修習を受けたのかということを明らかにする情報といえます。また、現在は、裁判官、検察官、弁護士のいずれになるにせよ、原則として司法修習を受けますので、ごく一部の例外を除いたほぼ全法律家が自分の修習期を持っています。
この修習期は、短い中で伝えるにしてはそれなりの情報量があり、なかなか良くできている部分があります。その一つは、非常にシンプルに自分の法律家としての経験年数を伝えることができるという点です。法律家は司法試験の受験歴や、他職経験の有無などで法律家としてのキャリアをスタートさせた年齢にばらつきがあるので、経験年数を示す指標として、年齢や、大学の卒業年次などより便利なのです。なお、副次的には、修習期を聞けば、法律家としての先輩後輩関係が分かりますし、年齢の割に、修習期が新しかったりすると、大学を出てすぐに司法試験を受けた訳ではないのかな、ということが分かるというようなこともあります。
2つ目は、修習期が分かれば、共通の知人を見つけるのに役に立つ場合がある点です。近時は合格者もずいぶん多いので、法曹界一般における共通の知人検索機能は低下したと思いますが、何年か法律家を経験していれば、様々な期の知人ができますので、何人かその期の知人の名前を挙げれば、共通の知人が見つかったりすることもあるのです。
経験年数が一番根本的な数字であるというのは、法律家に学歴はさほど関係ない一方、何はともあれ経験が大事であるという観念が存在していることを象徴しているのかもしれません。
なお、似たように、法律家としてのキャリアを表す指標に弁護士の登録番号というものがありまして、これは、弁護士資格を有する人が、弁護士として登録した際に与えられる番号です。日本の場合、多くの弁護士は、研修所を卒業すると同時に登録をしますので、これも聞く人が聞けば、修習期が推測できる数字となります。しかし、こちらについては、当然のことながら、裁判官や検察官は持っていませんし、裁判官や検察官をやったり、弁護士登録をせずに企業の法務部に努めたりした後に弁護士になったりすると、登録番号から推測される修習期と、実際の修習期がずれたりします。
ちなみに、弁護士が最高裁判事になるなどして、いったん弁護士登録を抹消した後、再登録する際、かつては、新しく番号が振られたのですが、数年前に、再登録の際には、もともとの番号が振られるように制度が変更になったようです。私が弁護士になる前の制度変更なので、その変更の趣旨を正確に理解しているわけではないのですが、少なくとも、弁護士にとって、登録番号はただの個人を識別するためのラベルにとどまらない意味を持つということなのだと思います。
説明が長くなりましたが、何が言いたいかと言いますと、私の修習期(58期)と、弁護士の登録番号(60098)は、聞く人が聞けば、修習期の割に若すぎる番号となっているのですが、一つには、そうなったのには正当な事情がありますので、特に怪しいわけではないということと、2つには、それにはかかわらず、私自身、何となく、修習期の割にやたらと若い登録番号についてはあまりいいたくないと思ったりしているということです。
このように思うということの背景には、私にも、法律家には経験年数の長さが重要という観念が染みついているのかもしれませんが、ともあれ、経験の割に実力がないなどといわれないよう日々精進したいと思います。