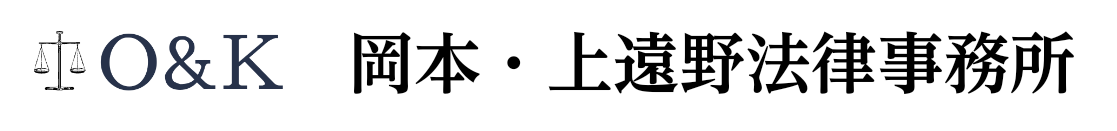裁判官の「心証」形成について(第3回)
1 訴訟の中盤における心証形成について
前回説明しましたように、訴訟の序盤は、裁判官が、当事者の主張の概要や、基本的な書証の有無やその内容を把握する時期といえます。もちろん、実際の訴訟において、今がどの段階にあるか教えてもらえるわけではないですが、訴訟の中盤というのは、裁判官が、各当事者の基本的な主張の枠組みと書証が出そろい、裁判官がその内容を把握した段階から始まるといってよいかと思います。
裁判官が基本的な主張や書証を把握した段階とはいいかえると、どの部分の当事者の主張が一致しており、どの部分に不一致があるのか、ということを把握し(当事者の主張が一致しない点を「争点」といいます。)、その点について、それぞれ当事者がどのような主張をしているのか、あるいはどのような証拠があるのか、ということを把握した段階ということができるでしょう。
このように分類した場合に、当事者間に争いがない点については、基本的には裁判官はそのとおりの事実があったものと扱いますので、この部分が特に議論されていくということはありません。また、当事者の主張が一致しない点であっても、それが訴訟の結論に影響を与えないような事実についての争いであれば、いってみれば、裁判官にとっては、「どちらでもよい」事実ですので、この部分も特に議論の対象とはならないでしょう。
しかし、争点当事者の主張が一致していない点であって、そのどちらの言い分が正しいかで、訴訟の結論が変わりうるもの(これを「争点」といったりします。)については最終的には裁判官は判決の中で、判断をする必要があります。したがって、現状の当事者の主張や証拠をみても、判断ができない、ということになれば、主張を補充したり、新しい証拠を出してもらう必要があります。訴訟の中盤というのはこのように争点について「深掘り」をしていく段階ということができます。なお、争点であれば同じように深掘りをする必要があるわけではありません。主張や証拠を見れば、議論を深めることなく、十分判断可能という場合もあるからです。
どのように深掘りしていくかは、裁判官の個性や、当事者の訴訟活動にもよろうかと思います。たとえば、争点がどこであるかの認識が、裁判官と当事者とで一致していて、かつ、当事者に的確な反論をする能力があれば、当事者が適宜反論を積み重ねていけば、自然と深掘りされていくことになるでしょうから、裁判官は、引き続き「交通整理」をしていればよいというような場合もあります。他方、裁判官が疑問を抱いている点が必ずしも当事者と同じとも限りませんし、必ずしも、当事者から的確な反論がされない場合もあります。そのような場合などは、裁判官は、当事者に対し、「こういった点についてはどう考えているのか」「この点についての反論はどうなるか」「こういう証拠はないのか」といった形で尋ねることになります。
なお、こうした疑問をぶつける行為をどれだけ積極的に行うかは裁判官の個性にもよります。疑問に思うことは積極的に尋ねる裁判官もいる一方で、きわめて慎重に行う裁判官もいるように思います。また、裁判官も、当事者の主張や立証という限られた情報の中で考えていますので、一時的には疑問を抱いたけれども、結果としては関係なかったということもあります。いずれにしても、訴訟の中盤は、このようにして争点を「深掘り」することで進んでいくといえます。
このようにして「深掘り」していく中で裁判官は必要な心証を得られることもあります。そうすればもちろんそれ以上深掘りする必要はありません。他方で、当事者の主張を聞いたり、証拠を出してもらっても、まだ判断できるかどうかわからない、ということになるものもあります。現在の日本の訴訟においては、そのような点を中心に当事者や、関係する当事者の尋問をして決着をつけることが一般的です。したがって、この段階以降は、争点を深掘りしていくとは別の作業が必要となりますので、この段階以降を訴訟の終盤というふうに呼びたいと思います。
2 当事者の対応について
以上のように整理するとすると、訴訟の中盤で当事者にとって必要なことは、いかに、争点について、裁判官の疑問に答えていくか、ということが重要といえます。したがって、裁判官が具体的な点について疑問があるというのであれば、それについて「うまく答える」ということが非常に重要となります。とはいえ、「うまく答える」というのがどのようなことかというのは場面によって、あるいは、手持ちの資料によっても異なるでしょう。
たとえば、裁判官がある資料の提出を求めており、自身がそうした証拠を有しており、かつ、当該証拠を提出することで自身が有利になるというのであれば、話は比較的簡単です。しかし、仮に言い分が正しいとしても常にそれを裏付ける資料を保有しているわけではありませんので、話は常に簡単というわけではありません。
例えば個人間で1000万円を貸したので返してほしいという訴訟において、被告側がそもそも借りていない、と言って争っているとして、裁判官が、契約書なり、借用証なりはないのか、ということを尋ねた(しかし、借用証は作成していない)というような事例を考えてみます。これは、裁判所としては、1000万円というのは大金ですから、個人間であっても、借用証くらい書いてもらうのが普通でそれがないのは、本当は貸していないからではないかという考えのもと尋ねていることが推測されます。いずれにしても、対応しなければ不利になることが想定されます。
こうした場合には、単に借用証を提出できないというのではなく、借用証を作成しなかった合理的な理由やその裏付け(例えば、何度も貸し借りをしていて、借用証がなくてもお金を返してくれないということは考えられなかったとか、何か価値のあるものを預かって、借用証の代用としたといったようなことがあるかもしれません。)、借用証以外でお金を渡したことが分かる資料(例えば振込の履歴など)を提出するといったことを検討する必要があるかもしれません(なお、当然の前提ですが、証拠を偽造したり、虚偽の主張をしてはいけないことは当然です。)。
あるいは、裁判官の前提に誤りがあるという可能性も否定はできません。しかし、仮にそうであっても、裁判官は判断者である以上、当事者としては、訴訟を有利に展開させるためには裁判官の前提が誤りであるかについてきちんと説明できなくてはなりません。
そして、そもそも、上述のように、(その是非は別として)裁判官が疑問に思っていることを当事者にすべて尋ねるというわけではありません。例えば先ほどの例でいうと、借用証がないなら、1000万円を貸したことは認めようがないと思って、追及すらしないという可能性だってあります。そのように考えると、裁判官が疑念を抱きそうなところはあらかじめ補強しておく必要があるともいえます。
要するに、この段階では、裁判官が疑問を持った部分(そしてそれが自分に不利になりうる部分)のみならず、裁判官が疑念を持つであろう部分を推測しそれに対応することが重要といえるでしょう。この点、当事者は、自分で事案を体験していることが多いため、いくつもの無意識の前提を有しており、それらについて裁判官にも説明しなくても分かってもらえると思ってしまいがちですが、裁判官は、当事者にとっては当然の前提を共有していません。したがって、当事者としては必要に応じて、裁判官に伝わっていない可能性のある無意識の前提についても説明する必要があります。訴訟を弁護士に依頼することの大きな利点の一つは、前提を共有しない(それでいて自分の味方をしてくれる)第三者の視点を入れられることにあるように思います。
3 和解について
なお、訴訟の中盤というのは、裁判官が和解を勧める一つのタイミングではないかと思います。これより前の段階ですと、裁判官も事案を把握できておらず、どのような和解にすべきか方向が定めにくく、他方で、このタイミングで和解は、当事者にとっても、訴訟による金銭的、時間的コストを省くことができるというメリットが生じるからです。もちろん、和解ですので、どんなに自分が有利であっても、いくばくかの譲歩は迫られますので、100%自分の思う結果にはなりません。まして、ある争点について判断が微妙ということであれば、それに応じた譲歩を迫られることもありますが、この点については、譲歩を迫られた部分だけで損をしたと考えるのではなく、上述した金銭的、時間的コストを省けるということも念頭に置く必要はあるでしょう。加えて、事案を自分で体験している当事者としては、それと一致しない前提で譲歩を迫られては納得しにくいということはあるでしょう。そして、この場合に裁判官はわかってくれないと憤慨するのは簡単です。しかし、この点についても、上記のように、裁判官は、事案を自分で体験していないということを念頭に、どのように説明すれば自分の意見を汲んでもらえるかということを考える方が生産的ですし、仮にそのための立証コストが非常に高いというのであれば、そう下コストも念頭に置いて和解を検討する必要があることは、現行制度上やむを得ないのではないかと思われます。このようなコストの見積もり、ひいては和解の利害得失の検討という意味でも、弁護士がお役に立てることがあるように思います。
4 終わりに
次回は、訴訟の終盤、すなわち、尋問をめぐる段階について説明したいと思います。