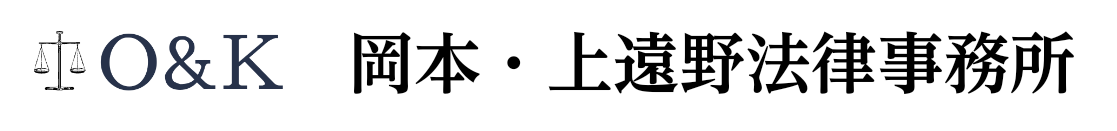民事裁判と和解(第2回)
裁判官は、自分の心証に従って和解を勧めているのか
以前に、裁判官の心証形成について書いたことがありますが、この点について触れる際には、まず、裁判官が結論をどちらだと考えているか、という意味における確信の程度という意味での「心証」と、いわゆる「印象」とを区別する必要があります。
そして、心証が前者の意味であることを前提とすると、結論から申し上げると、裁判官が自らが「イニシアチブをとって」和解を勧める場合には、自分の心証に従って行っていると思います。ただ、この点については以下の点に注意する必要があると思います。
すなわち、以前にお書きした通り、裁判所の心証というのは、訴訟の進行度合いに応じて、その確度は異なるという点です。ごくかいつまんで言えば、その確度は、訴訟が進行するにつれて高まります。すなわち、訴訟の序盤では、そこまで心証の確度は高くありません。それでも、あえて、心証と反対の和解を勧めるということはしないと思いますが、裁判官の立場からすれば、心証を開示した後に心証が変わってしまうと、時点が異なるとはいえ、裁判官が事実と異なる説明をしたとも評価しうる事態となり、裁判官の信頼を損なうなどと考え、心証が変わらないとしても、訴訟の序盤から結論を決めつけていたと思われる可能性があるので、いずれにしても好ましくないため、心証を開示しないか、するとしても極めて抑制的にするべきであるという方も一定数おられるように思います。そういったタイプの裁判官が訴訟の序盤で和解を試みる場合は、心証にしたがって、というよりは、当事者の意見や訴訟外の事情なども聞きつつ、どちらかというと「受け身の」和解を試みることになりがちです。
他方で、暫定的な心証であるということをきちんと当事者に伝えれば上記のような事態は問題ではない、という考えの裁判官もいると思いますが(なお、私は尊敬する裁判官から、そのような考え方を教わりました。)、弁護士になってからの私の限られた経験から得た印象にはなりますが、そのような方は少数派であるようには思います。
したがって、訴訟の序盤の段階では、そもそも「イニシアチブをとって」、すなわち積極的に心証を開示して和解を勧めるということをしない裁判官も多く、他方で、心証を開示する裁判官であっても、その心証はあくまで暫定的なものでありますので、良くも悪くも後に変り得るものと考えておく必要はあるでしょう。
逆に訴訟の終盤、殊に尋問が終わった段階というのは、多くの場合、その審級においては、後は裁判所が判決を書くだけ、という段階ですから、基本的には、確度は極めて高く、その段階で、裁判官が判決であれば結論はこうなる、という説明をしたのであれば、基本的には文字通り受け取るべきだと思います。
訴訟の中盤というのは、端的にいえば、上記の中間に位置しているように思います。
以上をまとめると、和解の利害得失を考えるにあたっては、訴訟の終盤に近付けば近づくほど、裁判所の示した心証通りの判決が出るであろうことを前提にする必要があるといえるでしょう。もう少し具体的にいえば、訴訟の序盤で言えば、裁判所の「暫定的」な心証を覆せる可能性がどの程度あるか、ということを考える必要があり、他方、訴訟の終盤にあっては、基本的には裁判所の心証は変わる可能性は低いことを前提に、控訴する場合(控訴する場合、もちろん、解決までの時間は少なくとも数か月程度余計にかかりますし、そのための費用も掛かります。)と比較する必要性が高くなるでしょう。
なお、上記は、基本的には第一審を念頭に記載したところになります。控訴審ではどうかといいますと、控訴審においては、既に第一審において、少なくとも、担当裁判官が判決しうると考える程度には、主張立証がされていることが前提となります。したがって、控訴審の裁判体がそれ以上の主張立証は必要ないと考えれば、1回で終わってしまう場合も多く、そうでなくても、まったくのゼロからスタートするわけではないので、上述した区別でいえば、いきなり終盤にあるといって差し支えないと思います。また、控訴審は第1審とも異なる部分があります。それは、第1審判決に対する不服は「控訴」である一方、控訴審判決に対する不服は「上告(ないし上告受理申立て)」であるという点です。どちらも同じ不服申立てではあるのですが、後者は、不服の理由が限定されています。これを正確に説明するのは紙幅を要しますし、今回の本筋から外れますので割愛してラフに言うと、上告審においては基本的に事実認定の不服については取り上げられない、ということができます。そういったこともあって、第一審判決が控訴審で覆る可能性と、控訴審判決が上告審で覆る可能性を比較すると、後者の方が圧倒的に低くなります。
言い換えると、控訴審で開示された心証は、第一審の終盤のように判決の結論と一致する可能性が高いばかりか、それが不服申し立てによって覆る可能性はより低いということになります。したがって、控訴審での和解については、判決より少しでも有利な内容になるのであれば受ける方が(少なくとも単純な経済合理性を考慮した場合)得になる場合が圧倒的に多い、ということになります。
今回は、ここまでといたします。